001
HATRA
DIALOGUE WITH KEISUKE NAGAMI
リミナル・ウェアを掲げる「HATRA」は、仮想と物理、場所やジェンダーの境界を融解させる、新たなファッションデザインのあり方を探求している。近年、クロスシミュレーションソフトウェアの導入や人工知能の応用を意欲的に実践し、デジタルツールによる身体表現を展開するデザイナー、長見佳祐との対話から、生成技術時代の創造性を明らかにしたい。2019年、Algorithmic Coutureを応用した初のコラボレーションとして公開された「AUBIK」の省察を通して、アルゴリズムによる制作の意義と今後の展望を問う。
リミナル・ウェア──場所、空間、ジェンダーを超える不確かな境界装置

シグネチャーアイテムの一つであるフーディから連想するように、HATRAは「部屋」というコンセプトを掲げ、ブランドがスタートしました。
2010年の設立時から「部屋のような着心地を外に持ち出せる、ポータブルな空間としての衣服」を提案してきました。
それから、近年では「リミナル・ウェア」へと活動の軸を拡張しているようにも見えます。
パンデミック下で、移動がままならなかったことが大きく影響しています。これまで「室内」や「部屋」について肯定的に考え、衣服を作ってきたはずなのに、移動できないのはなぜこんなに辛いのかと。部屋に閉じこもることで人間が感じる不足感とは何かと思ったときに「リミナリティ」という言葉が目に入ったんです。
リミナルという言葉には、辞書的に「境界」という意味があり、またネットミーム的には「リミナルスペース」も連想します。
朝方のサービスエリアや、廃墟空間に共通のイメージを見いだすことができますね。レベッカ・ソルニットの『ウォークス──歩くことの精神史』に影響を受けたのですが、リミナリティには「既存の秩序が消尽する不確かな界/閾」という意味もあります。歩くことや移動、巡礼を通して、自らの境界性を超えていくことにも当てはめられると思っているんです。


以前、衣服は人に尊厳を与えるものであるとおっしゃっていたのを思い浮かべました。例えば、背広を着るとあらゆる人が威厳を担保できる。衣服は、制度、階級、ジェンダーといった社会的な境界を飛び越える装置にもなりえるという意味だと解釈しました。
仮想と物理における衣服制作についても意味を織り込んでいます。メタバース空間における高解像度のアバターを見たときに、重力による身体やテキスタイルの動きを十分に考慮できていない状態があったとする。あるいは、人間身体のプロポーションを逸脱した、3頭身のプロポーションでもアバターの表象が成立していたとする。それでもなお、自然に思える状況がおもしろいと思っていて。
まさにそれが、物理と仮想の境界を超える「リミナル・ウェア」であると。
デザインの手法が依拠している既存の秩序やコードから解き放たれて、どちらでもいいという気持ちになったとき、HATRAらしさの純度が結晶化する。そんな瞬間を目指しています。


アバター制作における「見えないもの」のデザイン
実際にHATRAは、YOYOGI MORIとの協業で、VRChat用のアバターを販売していますね。
YOYOGI MORIのアバターを購入したことがきっかけでご連絡をいただき、コラボレーションがスタートしました。僕はデザイナー兼モデラーとして、プロジェクトに参画しています。
アバター制作の現場はどのような様子だったのでしょうか?
アバター制作は多くの工程を分業で進めます。具体的には、キャラクターデザインから、アバターの身体にあたる素体、服装のそれぞれのモデリングをチームで連携しながら進める必要があります。
デザイナー兼モデラーとしては、実際どのような制作をされたのですか?
僕はクロスシミュレーションソフトCLO3Dを扱えるため、服装のデザインから基礎モデリングまでを共通して担当しました。ただ、その後には、素体と服装の細かな調整や、メタバース環境に適応可能なポリゴン数の制御など、たくさんの方々の手を介しながら、利用可能なアバターに仕上がっていきます。

映画やアニメーションの現場にも見られるような、モデリングとデザインの綿密な連携によって、アバター制作は実現しているというわけですね。
そうですね。骨にあたるボーンの制御を行うリギングや、シワを表現するテクスチャ画像データの作成にも相当なエネルギーをかけています。自動化によって実現できることもありますが、リアルタイムで相互作用するアバター制作は、職人芸によって成立している部分も大きいんです。
CGツールを介し、バーチャル環境において成立するアバターの条件設定を行う中で、次第に「見えないもの」が設計の対象となっているのだなと感じます。
そうだと思います。バーチャルヒューマンSayaを開発するTELYUKAの皆さんにお話を聞いたことがあるのですが、アバターの瞳孔の揺れをデザインしていると言っていたのが興味深くて。実際には、見えないし、知覚できないかもしれないけれど、ハイパーミクロなレベルの設計行為によって、アバターに生き生きした状態を作り出せるのではないかと思ったんです。
表層と無意味───人工知能とファッションデザイン
コレクションデザインでは、生成AIを使って制作を進めていらっしゃると聞いています。
実際にやっていることと言えば、テキストやイメージを入力して、画像を生成するという単純な行為の連続なんです。とはいえ、ファッションデザインにとって、最も魅力的だと考えているのは、言語モデルの多次元意味空間の中に語彙やデザイン画を落としたとき、潜在的な意味の広がりが垣間見える体験ですね。
というと?
例えば「リンゴの服」をキーワードとして入力すると、スティーブ・ジョブズが出てきたり、あるいは服を着たリンゴが出てきたりとか、本来自明だと思ってるベクトル以外の、言葉の発散性が無意味に広がるわけです。感覚的には自分の意識が全ての時間軸に存在してるという感じ。服を作っている途中から、作る前、作った後まで、全ての時間で服づくりに向き合えているような感覚がするんです。


完全に意味が剥ぎ取られた「無意味」が、イメージや言語として膨大に降ってくる状況が、ファッションデザイナーにとって求められることであると言えるわけですね。
「表層の力」の重要性を強調したいです。ファッションの歴史は、うんちくやディテール、機能性に関わる重い意味の側面もありますが、人工知能全盛の時代になって改めて、表層を無尽蔵に扱うファッションデザインの拡散的な力の重要性を感じています。
意味の解体と再構築のプロセスが、ファッションデザインの中心にあり、それらは表層のコラージュによって成立していたとも言えるわけですね。AI開発者の三宅陽一郎さんは、こうした特性を踏まえ「想起装置」としての人工知能について言及しています。
極端に言えば、ロンTにトレンチコートがプリントされているトロンプ・ルイユ(だまし絵)を、良いと思わせることができる力が、表層の力です。「機能的にできてる風」の軽薄な意味がTシャツにへばりついていているだけだとしても、実際のところ日常で消費するトレンチコートにはすでに、かつての軍服としての機能性を発揮しない。本来、その意味を解体する行為は、布にハサミを入れたり、トワルを作ってみないとわからないことでも、仮想空間で可能になったことが画期的だと思っているんです。
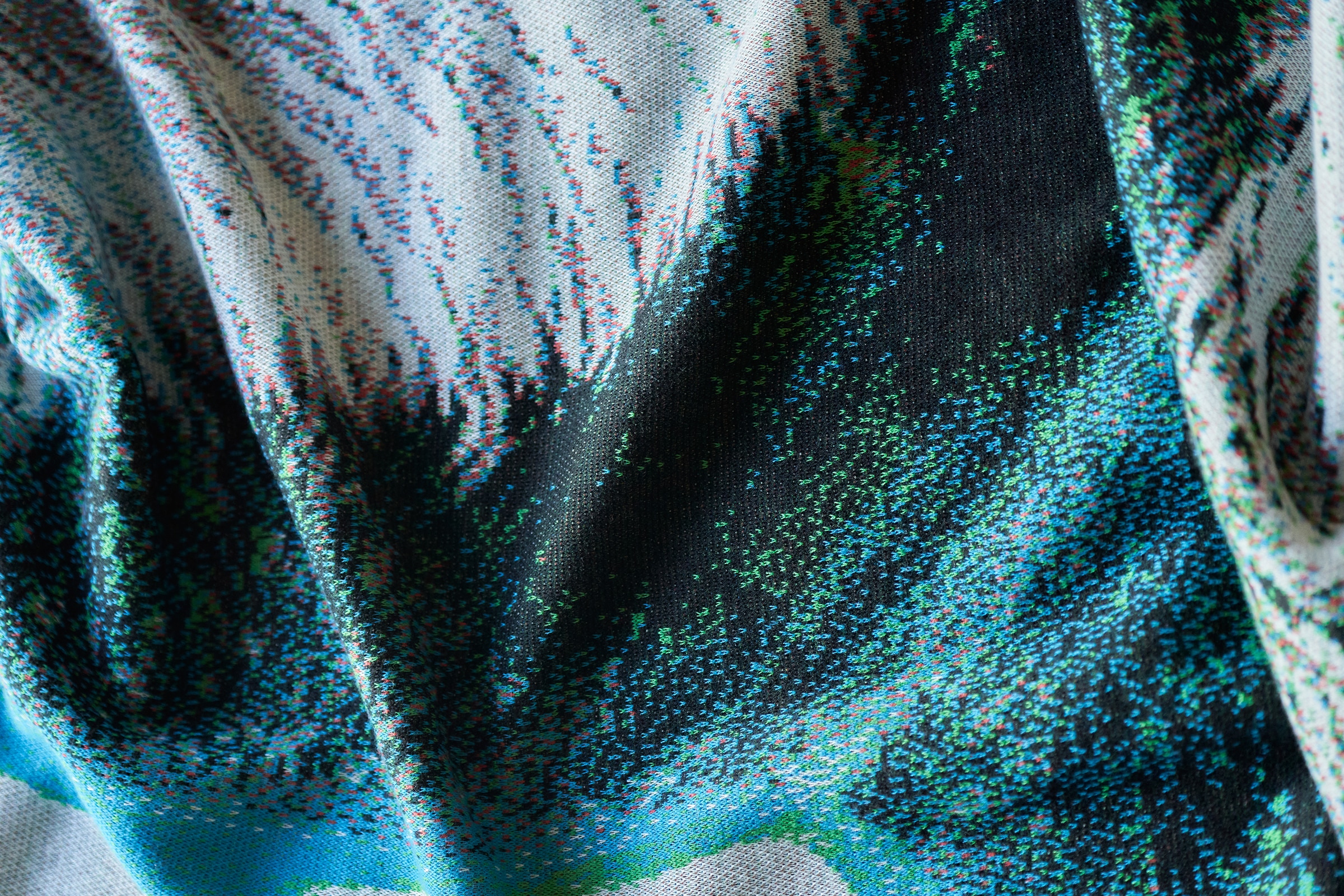
AUBIKを振り返る──無慈悲な生成、コモンズとしてのパターン
2019年に、HATRAとは、Algorithmic Coutureを活用したSynfluxとして初のコラボレーション「AUBIK」を共同制作しました。
Algorithmic Coutureにおける「廃棄削減」は、機械に与える報酬として適切だなと思っています。プログラムやアルゴリズムが効果を創出できる余地として、生産効率が良く、環境に良いというのは、全く非の打ち所のない現実との接地面だなと。
そんな報酬設定が与えられたプログラムから出力されたAUBIKのパターンには、どのような印象を持たれましたか?
そんな最適化のアルゴリズムを応用してみると、たしかに人間が1000年近くかけて作り上げてきた型紙に近似しているけれど、全く違う目線から作られたものが出力される。その禍々しさ───いわば、人間と機械のあいだに存在する差異が鮮明になること。僕にとっては、それが一番見たかったものです。


人間と機械のあいだの差異は、ファッションデザインの思考方法にどのような影響を与えるでしょうか?
企画であれ、縫製であれ、検品であれ、服の制作に関わるどのような人々も、審美的な判断をしていると言えます。すべてわたしたちが袖を通すまでの重要な営みですが、想像力をブロックしている面もあります。既存の審美感に依存する考え方を変えるという点では、Algorithmic Coutureが突きつける「生成の無慈悲さ」はすごく頼もしいなと思います。
無慈悲な生成を、ファッションデザインの創造性へと転用することは可能でしょうか?
AUBIKのショルダーをよく見てみると、異常な形状への再設計が見られます。初めて確認したときは、自分には持ち得ない目を与えられた感覚がありました。オーセンティックな洋服の作り方を、足元から崩される感覚というのは、おそらくデザイナーであれば誰しも気持ち良いと感じる部分はあるのではないでしょうか。
これからのAlgorithmic Coutureの展開に期待することがあれば教えてください。
Algorithmic Coutureが生み出す廃棄減少や設計の合理化という価値が、サービスとして波及していくなかで、パターンがもつ共有知としての役割がどのように位置付けられるかが気になっています。型紙は「原型」として、誰にでも利用できるような形式になっているものもありますから、システムから生まれたコンセプトが、コモンズとしてブレイクスルーする可能性にも期待したいと思います。


取材補助: 増野朱菜
文章構成:川崎和也、藤嶋陽子
キーワード執筆:川崎和也
カバービジュアル:田巻海
撮影: 吉屋亮
写真提供: HATRA
Date: Febrary 8, 2024